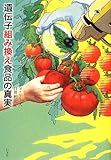遺伝子組み換え ゲノム編集 食卓での選択と安全性
遺伝子組み換え食品の仕組みと遺伝子導入の原理
遺伝子組み換え技術は、目的とする性質を持つ遺伝子を異なる種の生物から取り出し、対象の植物や動物に導入する技術です。例えば、微生物が持つ有用な遺伝子を農作物に組み込むことで、病害虫への耐性や除草剤耐性を付与します。この技術の根本的な特徴は、「自然界では起こらない遺伝子の組み合わせ」を人為的に作り出す点にあります。
組み換えプロセスでは、導入された外来遺伝子は最終的な製品に残ります。つまり、完成した遺伝子組み換え食品には、元々その生物が持っていなかった遺伝子が組み込まれたままの状態で販売されるのです。この外来遺伝子の存在が、安全性審査と表示義務の対象となる重要なポイントです。日本で流通する遺伝子組み換え食品は、トウモロコシ、大豆、ナタネなど限定的で、すべて厳格な安全性審査を経ています。
主な遺伝子組み換え食品の用途は、植物油、飼料、加工食品の原材料となることがほとんどです。食卓で見かける加工食品の多くに使用されており、特に動物飼料として大量に利用されているため、意図せず摂取している可能性は極めて高いのです。
ゲノム編集作物の仕組みと自然突然変異の活用
ゲノム編集技術は、その生物が本来持つゲノム(DNA全体)の中の特定の場所を切り、そこで生じた修復ミスを利用して、自然に起こりうる突然変異を人為的に誘発する技術です。「CRISPR/Cas9」などの「はさみ酵素」を使い、狙った場所を精密に切断することで、目的の性質を効率的に持たせることができます。
自然界でも、紫外線などによってDNAが切断され、修復ミスにより突然変異が起こります。ゲノム編集は、この自然現象を人為的に制御することで、品種改良の時間を大幅に短縮できる革新的な技術なのです。ゲノム編集プロセスでは、修復を終えた後に「はさみ酵素」は細胞内で分解され、最終製品には外来遺伝子が残りません。
実用化されたゲノム編集食品として、GABA高蓄積トマト(血圧上昇抑制効果が約4~5倍)や可食部増量マダイ(可食部が約2割増加)などが存在します。現在、研究段階にある天然毒素低減ジャガイモや穂発芽耐性コムギなど、主婦の関心が高い農作物の改善が進められています。
ゲノム編集と遺伝子組み換え 食品表示制度の大きな違い
食品衛生法による規制の違いは、主婦にとって最も実践的な判断基準です。遺伝子組み換え食品は、国が安全性審査を実施し、その結果をもとに承認する仕組みになっており、外来遺伝子を含むすべての製品に表示義務があります。一方、ゲノム編集食品のうち、外来遺伝子を含まないSDN-1やSDN-2タイプは、カルタヘナ法(生物多様性関連法)の規制対象外となるため、国による承認審査は不要です。
ただし、この審査が不要というのは、「自然界でも起こりうる変異だから安全とみなされた」という考え方に基づいています。2024年4月から、ゲノム編集技術応用食品を市場に出すには、開発者が消費者庁に情報を届け出る制度がスタートしました。届け出された情報は消費者庁のウェブサイトで公表されているため、購入前に確認することが可能です。表示義務がないため、商品パッケージには「ゲノム編集使用」と書かれていない製品がほとんどです。
遺伝子組み換え食品の表示義務は、大豆油、コーン油、砂糖、水飴、異性化液糖など、主要な加工食品原料を対象としています。これらの製品には「遺伝子組み換え」または「遺伝子組み換え不分別」と表示されるため、購入時に識別しやすいのです。
ゲノム編集食品のオフターゲット変異と安全性確認
ゲノム編集で懸念されるのが「オフターゲット変異」です。これは、狙った遺伝子以外の似た配列も切断してしまう現象です。ゲノム編集では、約1兆分の1という極めて低い確率で、狙った塩基配列のみを識別して切断しますが、例外的に類似配列が切断されることがあります。
しかし、これは従来の品種改良でも起こっていた現象なのです。放射線照射や化学物質による人為的突然変異では、数千箇所の変異が同時に起こるのに対し、ゲノム編集では目的以外の遺伝子を切断する可能性は圧倒的に低いのです。ゲノム編集を行った後の選抜段階では、本来目的とする塩基配列と似た配列に変異がないか確認し、安全と判定されたものだけが実用化に進みます。
主婦が購入時に気になる点は、「見た目は普通でも何か入っていないか」という不安かもしれません。ゲノム編集食品は、外観上は通常の農作物と変わらず、成分も自然に起こりうる範囲の変化のみです。むしろ、従来の育種技術で作られた品種よりも、目的の性質に特化した品種が効率的に開発されるため、不意な副作用のリスクは低いと言えます。
ゲノム編集と遺伝子組み換え 家庭での選択時のポイント
現在、日本の食卓に上る食品のうち、遺伝子組み換え由来成分を含むものは極めて多いです。大豆油、コーン油、異性化液糖など、加工食品の基本的な原料として大量に使用されています。これらは安全性審査を経ているため、「安全でない製品は流通していない」という理解が必要です。一方、ゲノム編集食品は、現在のところ日本国内で市場流通しているものは限定的ですが、届け出情報により追跡が可能です。
主婦として実践的な判断をするなら、次の三つのポイントが重要です。
①遺伝子組み換え食品で表示されているものは、国が承認した安全な製品であることの証です。表示があるからといって「避けるべき食品」ではなく、「確認済み」と理解しましょう。
②ゲノム編集食品については、消費者庁のウェブサイトで届け出情報が公表されているため、興味がある場合は事前に確認できます。現在、日本に流通しているゲノム編集食品として届け出られたものはまだ少ないですが、今後の動向を注視する価値があります。
③表示がない=不安な食品、という過度な解釈は避けましょう。食品衛生法により、すべての食品はその安全性が義務付けられており、遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品、従来品のいずれもが同等の安全基準で出荷されています。
育種の歴史を振り返ると、人類は何千年も前から、自然の突然変異を選抜することで品種改良を行ってきました。ゲノム編集は、その効率を格段に高めた技術に過ぎません。遺伝子組み換えは、自然界では起こらない遺伝子の組み合わせを実現する技術ですが、審査制度があるからこそ、市場に出ているすべての製品が安全と言えるのです。
毎日の食卓で、完璧な選別をしようとするのではなく、基本的な仕組みを理解した上で、購入時に表示を確認する習慣を持つことが、最も実践的で精神的にも健全な選択につながるでしょう。
【遺伝子組み換えとゲノム編集の規制体系参考情報】
農林水産技術会議によるゲノム編集解説(新しい育種技術の原理と実用化事例の詳細)
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genome_editing_leaflet/genome_editing_leaflet.html
国立研究開発法人 バイオテクノロジー情報提供サイト(両技術の法的規制の詳細な比較)
https://cbijapan.com/faq/student/412/
消費者庁ゲノム編集食品届出情報(市場流通予定のゲノム編集食品の最新情報)
https://www.caa.go.jp/